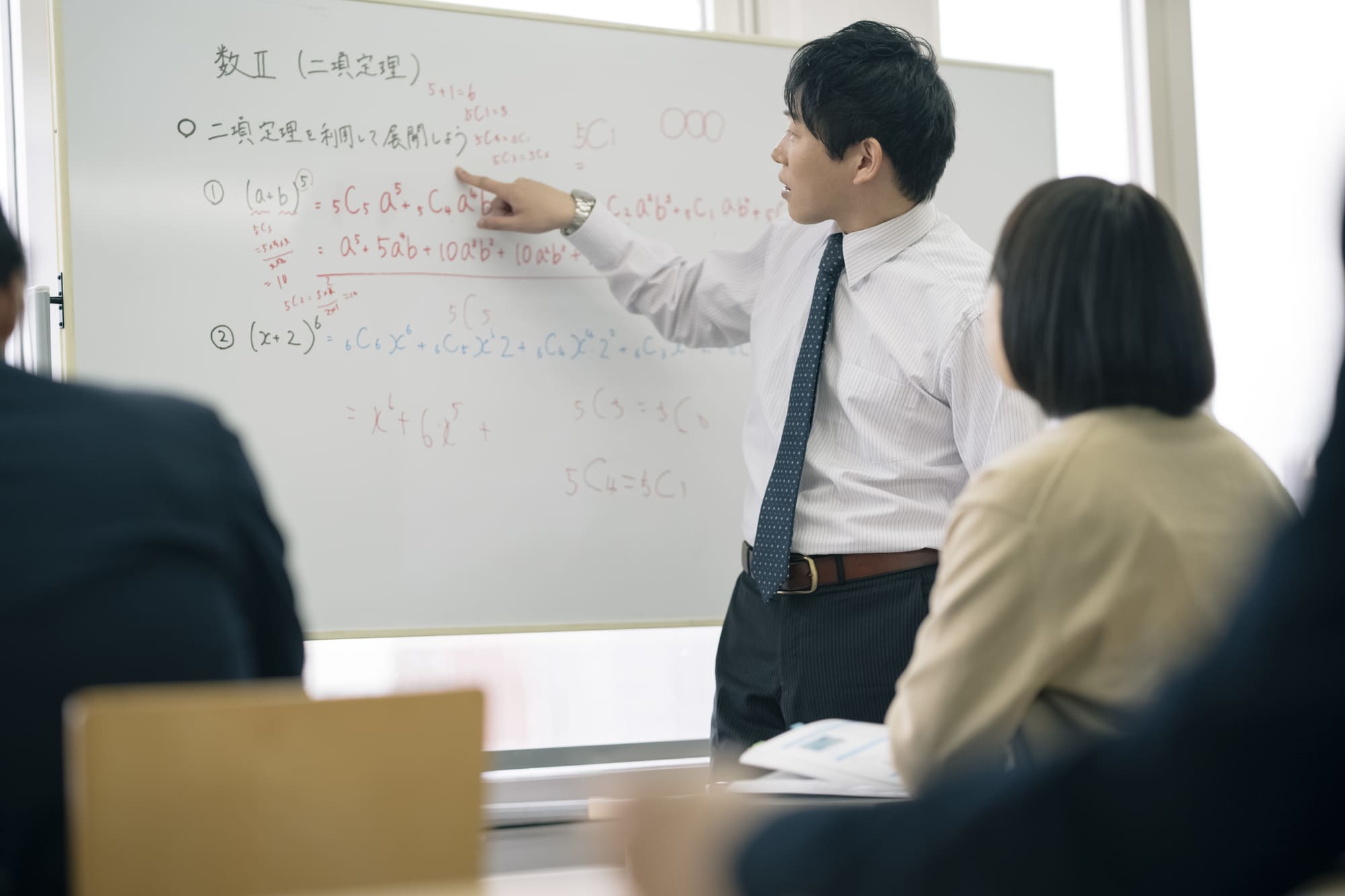予備校や塾に通う生徒は、年々低年齢化が進んでいる傾向です。高校在学中、実に全体の約3割の生徒が予備校に通っているという統計データがあります。それでは、大学受験に備えて予備校に通う学年は何年生が適しているのかをご存知でしょうか?
「予備校にはいつから通えばいい?」「高校3年生からでも間に合う?」と、これから大学受験を目指す人は考えていることでしょう。
今回は、予備校に通うタイミングについて解説します。
高校2年時で4割弱の生徒が予備校に通っている
マーケティング会社の統計調査では、およそ高校2年から3年にかけて最も多くの生徒が予備校に通っているというデータがあります。これは、生徒が進学を目指す大学にもよりますが、学校区分によって予備校に通うタイミングは異なるのが一般的です。
例えば、進学校は高校1年生時で予備校に通う生徒が多く、これは授業の進度が一般的な学校より速いことが理由とされています。進学校の特進クラスでは、遅くとも1年時で高校の授業範囲が終わり、大学受験対策へのカリキュラムに移行するケースも珍しくありません。
しかし、進学校の生徒が予備校に通うのには理由があります。なぜなら、授業進度が速いからこそ、ついていけない生徒は授業外で補う必要があるからです。1年時に差がついてしまうと取り返すことが困難になるため、基礎学習を固めて大学受験に必要があります。
一方、公立高校の授業進度は緩やかで、進学校のように授業で徹底した大学受験用のカリキュラムを組んでいるわけではありません。そのため、学校の授業では基本的に教科書の範囲内で基礎学力の向上を目的にしています。
そのため、本格的に受験対策するのであれば、できる限り早期に予備校通いを始めるとよいでしょう。進学する大学のレベルによって通うタイミングに個人差があり、倍率の高い難関校ほど高1から通う生徒が多い傾向です。しかし、一般的に公立校の生徒は、高2の2学期から高3の春先から通う生徒が多いとされています。
早いうちからの予備校通いが、大学受験に有利と考えられているのが一般的です。目的の大学に合格するのであれば、できるだけ早期に予備校に通うのがよいでしょう。
予備校に通わず大学受験する場合
基本的に学校の授業は、教科書の範囲に基づいて行われるものです。そのため、受験する大学によっては試験範囲をカバーしきれなかったり、合格の指標がわからなかったりする場合があります。
しかし、大学受験はもとより、予備校に通う費用は安いものではありません。家庭の事情や個人の考えなどを理由に、予備校に通わず独学のみで合格することは可能です。受験する大学のレベルが上がるほど難易度が高くなりますが、ポイントを押さえて勉強に取り組むことが重要になります。
まず、効率的な勉強スケジュール、試験範囲の把握、わからない問題を解決できる環境を自分で作り上げることが条件です。本来、予備校が用意する環境作りを自身で行なう必要があります。特に独学の場合、モチベーション維持が不可欠です。周りには競争相手の予備校生がいないため、客観的に自己評価できる環境を作りましょう。
また、自分以外に独学で大学受験に臨む仲間を見つけ、共通の目的を持った者同士で知識とモチベーションの共有で協力し合うのも有効です。
まとめ
大学受験に向け、予備校に通うタイミングは早いほうが良いです。一般的には2年~3年の時期が多く、進学校の生徒や難関大学受験を目指す場合、1年生から通うのがよいとされています。
重要なのは、大学を受験する目的と学力レベルに合わせた計画的な勉強です。大学受験が目的となり、ただ通っているだけでは意味がありません。また、必ずしも予備校に通わなければならないわけではなく、通う意味と目標を持つことが大切です。
なぜ予備校に通うのか、目標達成のためにどうするべきかを考え、自分にとって後悔のないベストな選択をしてください。